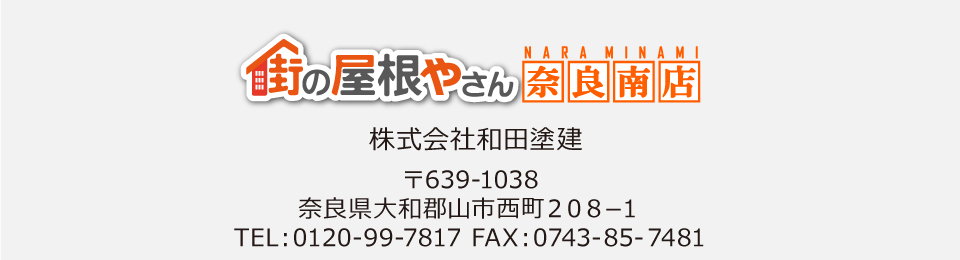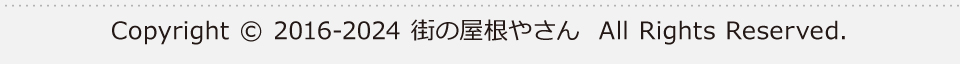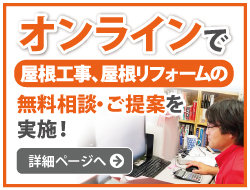
今回は、生駒市にある築50年以上の納屋の瓦屋根について、現場調査を行ってきました。お施主様から「屋根が崩れてしまい、隣の家に被害を及ぼさないか心配だ」とのお問合せを受け、早急に現地確認へ。
長年、風雨にさらされてきた瓦屋根。実際に現場で確認すると、予想以上に劣化が進んでおり、安全面からも早急な対応が必要な状態でした。そのため今回は、安全面を第一に考え、解体を含む屋根の全面的な改修工事をご提案しております。


≪見た目以上に深刻な劣化が進行≫
こちらの写真は屋根全体の様子です。一見するとまだ形は保たれているように見えますが、瓦の色ムラや浮きが多く見受けられ、長年の劣化が進んでいる状態です。また、瓦の色ムラが顕著で、特に白っぽく変色している部分は、表面の防水性が失われてきている証拠です。
このような状態は、雨漏りのリスクが高まっているだけでなく、風による瓦の飛散事故の危険性もあります。築50年以上ということもあり、部分補修ではなく、屋根全体の解体と屋根の新設をご提案させて頂きました。


これは屋根の最上部、棟(むね)瓦の部分です。棟瓦は、屋根の両面の接合部分を覆っており、雨水の侵入を防ぐ非常に重要な役割を担っています。
写真では、棟瓦が波打つようにずれているのがわかります。このままでは台風や強風で崩れる可能性が高く、崩落すれば下の瓦を巻き込んで大きな破損につながりかねません。
また、棟瓦の下に詰められている「葺き土(ふきつち)」が風化して流れ出てしまうと、さらに瓦の固定力が落ちてしまいます。本来なら棟瓦を一度すべて撤去し、補強材を入れて積み直す工事(棟積み直し)が必要ですが瓦屋根全体の劣化が激しいため棟積直し工事ではなく、瓦屋根を解体後新しく屋根を新設した方がいいでしょう。
屋根のいちばん上の“てっぺん”部分に、瓦がずらーっと積まれているのを見たことありませんか?
あの部分を「棟(むね)」といいます。屋根の角やてっぺんで、瓦を横向きに重ねているところです。
この棟は、お家の屋根を雨や風から守る大切な部分。ですが、年数が経つと地震や台風、経年劣化でガタついたり、瓦がズレてしまうことがあります。
棟が弱ると、そこから雨水が入り込み、屋根の下地や柱が傷んでしまうんです。
そして最悪、瓦が落ちてしまうとご家族やご近所の方の安全にも関わる重大なトラブルになりかねません。
名前のとおり、一度壊れかけた棟の瓦を全部はずして、もう一度しっかり積み直す工事です!
簡単に言うと…
→ ズレたり、落ちそうになっている瓦をきれいに外します。
→ 中に入っている昔の「土」や「接着材」がボロボロになってることが多いので、新しい補強材(南蛮漆喰など)を入れて、しっかり下地を作ります。
→ 見た目もきれいに、でも中はがっちり固定して、これからの台風や地震でも安心できるように仕上げます。


こちらの写真では、瓦が一部欠けて穴が開いてしまっている状態が確認できます。瓦の割れ目からは下地が見えており、この状態では雨が降るたびに屋根内部へ水が浸入することになります。
放置してしまうと、雨漏りだけでなく、屋根裏の木材腐食やカビの原因にもなり、建物全体の耐久性を低下させてしまいます。
このような破損瓦は、破損箇所だけを新しい瓦に交換する方法もありますが、今回は全体的な老朽化が進んでいるため、屋根全体の解体と屋根新設が最適と判断しました。

この写真は、屋根の「隅棟(すみむね)」と呼ばれる、屋根の斜めの角にあたる部分です。
瓦が数枚、ずれて浮き上がっているのが分かりますよね。実はこの状態、とても危険なんです。
瓦が外れかけていて、中の下地(粘土や漆喰)がむき出しになっている状態
この隙間から雨水が入り、下の木材を腐らせる可能性があります
強風や地震が来た時に、瓦が落下する恐れも
とくに写真のように瓦の下に大きな隙間が見えてしまっている状態は、すでに劣化が進んでいる証拠です。
瓦をそのまま戻しても根本的な解決にはならないため、土台からしっかり補修・積み直す必要があります。
この状態だと以下のような問題が出てきます。
雨水が軒裏から建物内に侵入する
落下して人や物に被害を与える危険性
美観の損失(瓦屋根特有のラインが乱れる)
この状態は放置すると非常に危険ですので、早急な修繕が必要です。


こちらは瓦屋根とトタン屋根の接合部、特に「谷(たに)部」と呼ばれる部分です。屋根と屋根が合わさってできる凹型の部分で、雨水が集中して流れやすい非常に重要な排水経路です。
谷とは、屋根の2面が合わさって雨水が集中するくぼみ状の部分で、ここを通って水がスムーズに流れ落ちていく仕組みです。雨水の通り道に砂埃やゴミがたまりやすい状態になっていて、排水性の低下が懸念されます。
現場調査では、以下の問題が確認出来ました。
谷部に落ち葉やゴミが溜まり、排水不良を起こしている
瓦が崩れかけ、屋根の構造が乱れている
隙間や隣接するトタン屋根との境目に破損箇所が見られる
植物の根などが瓦の間に侵入している
このまま放置すると、雨水が正しく排水されず、雨漏りや屋根下地の腐食、さらには瓦の落下事故などにつながるリスクがあるので、谷板金の交換をご提案させて頂きました。
谷板金(たにばんきん)の交換 谷の排水部分には「板金(はんきん)」と呼ばれる金属が敷かれていることが多く、これが錆びたり腐食している場合は新品に張り替える必要があります。
棟(むね)部分
→ 棟瓦のズレ・浮き上がり、内部の土の流出により崩壊寸前。
→ 強風・地震時に瓦の落下リスクあり。
隅棟(すみむね)
→ 瓦の歪みと隙間、内部構造の露出。
→ 雨水浸入と瓦落下の危険性。
軒先(のきさき)
→ 瓦の浮き・曲がり、先端の瓦の劣化あり。
→ 美観の低下+雨漏り・落下リスク。
谷(たに)部分
→ 谷板金のサビ、瓦の食い込み・ズレ。
→ 雨漏り・排水不良の原因に。
【屋根全体の解体・撤去】
→ 著しく劣化しているため、一度すべて解体。
【屋根の新設工事】
→ 構造からやり直し、安全で長持ちする屋根へ全面リフォーム。
【谷板金の交換】
→ 錆びた金属部分を耐久性のある新しい板金に交換し、雨水排水を確保
今回の屋根は、解体後に新たな屋根材を使用して全面改修を行う予定です。従来の瓦は重量があるため、建物に負担がかかりやすいですが、今回は「ガルバリウム鋼板(こうはん)」という軽量で錆びにくい金属屋根材を採用予定です。
この素材は、昔の納屋の構造にも相性がよく、耐震性が向上し、長く安心して使用していただけます。また、施工後のメンテナンスも比較的簡単で、将来的な維持コストも抑えることができます。

今回の現場は、築年数が50年を超える納屋ということもあり、屋根全体の老朽化が進んでいました。特に棟瓦のズレは深刻で、強風の影響で崩れる可能性もあり、ご近所への被害も懸念される状態でした。
このような古い瓦屋根は、見た目に大きな異常がなくても内部の構造が劣化していることが多く、早めの点検・対応が重要です。今回は屋根をすべて解体し、軽量で耐久性のある屋根材を用いて新設することで、今後も安心して使っていただけるようなご提案をいたしました。
屋根のことで少しでも不安を感じられている方は、ぜひ一度、無料の現地調査をご利用ください。安全で快適な住まいづくりを、私たちが全力でサポートいたします。
現場調査・お見積りは無料で行っています。
📞 お問い合わせ先:0120-99-7817(9時~20時受付)
メールのご相談はこちらをクリック➡(24時間受付)
皆さまのご依頼を心よりお待ちしております!
街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん奈良南店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2025 街の屋根やさん All Rights Reserved.